 あごの骨の中では こんな風に歯が作られて行っています。 |
歯の構造とできかた
歯の構造、、、これはどこでも書いてあるし、図で見てもらったら分かるのであんまり書きませんが
エナメル質、象牙質、セメント質、そして歯髄と言うものでできています。
この歯髄っていうのが、いわいる歯の神経と呼ばれるもの、
まずどうして歯の神経と呼ばれているのか、という説明からしましょう。
この歯髄という組織、神経はもちろんですが、毛細血管、その他の組織細胞
からなる普通のお肉、、、です。
ところがこの神経、ふだんは硬い歯の組織で囲まれており、普通の皮膚の神経が感じる熱い冷たい
痛い、ソフトな、といった刺激に対する反応は必要ありません。
という事でもともとこの歯髄の中の神経は、熱い冷たい、削った、触った、などという刺激に対して
すべて、≪痛い≫という反応しかしません。
この痛み、、ですが、歯を削ったときなど、どのようにして神経が興奮するのか?
じつははっきりした事はまだ研究中です。(何個かの説はありますが、)
さてそれでは歯のできかた、ですが、これが結構複雑です。
まず歯というものは骨の中で作られます。何から作られるかというと、もちろん細胞。
骨の中の歯嚢(しのうと読む)という袋が出来、そのなかに
エナメル質を作る細胞(エナメル芽細胞)、象牙質を作る細胞(象牙芽細胞)、というのが並びます。
ちょうど子宮のなかで赤ちゃんができてくるのと同じように、、、。
エナメル芽細胞と、象牙芽細胞の並び方はちょうどエナメル質と象牙質の境目の所。
そこからそれぞれがエナメル質、象牙質を作って行くわけです。
エナメル芽細胞
↑
○○○○○○○○○○○○○○○○
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
○○○○○○○○○○○○○○○○
↓
象牙芽細胞
そこから細胞はそれぞれエナメル質、象牙質を作って、細胞同士は離れて行く、、、。
そう、エナメル質、象牙質のなかには細胞がありません。つめとか髪の毛のように
細胞から作られた硬い組織という事です。ですからこれらそのものは削っても何しても
痛みを感じる事はないんです。
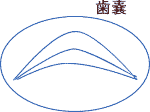
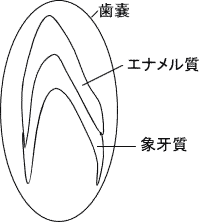
そしてこのように始まった歯の制作、、象牙芽細胞が
内側に入っていった所が歯髄となり、外にはエナメル質が作られていきます。
これであの複雑な形になっていく、、というのは不思議としか言いようがありません。

そして歯が生えると同時にエナメル芽細胞は歯の表面から
当然失われるということになります。(だから歯には再生能力が無いという事で
欠損が起きた場合、削ってつめるしかない、、という事になります。)

内側に入って行った細胞組織は、どんどん細長くかたちづくられ、最後には
根っこの先に穴を残して、そこから神経、血管が入り込み、中の歯髄組織の細胞に
栄養と、酸素を送るという事になります。
よく神経を取るといいますが、要はこの歯髄を細くなった根っこの先でちぎって、
ふたをして、無理矢理持たせちゃいましょう、、という治療なんです。
ですから、できる限り、なるべく、神経、歯髄というものは、簡単に取らない歯医者が
良い歯医者っていわれるんです。
(痛みや、炎症、細菌感染、など、どうしても歯髄を取らなくてはいけない
場合という事も非常に多いいですが、、、。)
そして、歯の成長は、歯髄が生きている限り、少しずつですが、進行しています。
作られ方からも分かるように、歯髄の一番そと、(歯髄と象牙質が接している所)
にはずっと象牙芽細胞が並んでいます。そして大人になっても、もしくは
外からの刺激を受けたときなども、象牙質を作ってより歯髄を細くして行こう、
象牙質の厚みを増して行こう、、とします。これが歯の成長です。
よく虫歯が痛んだのに、しばらくしたら痛みが無くなったとか、せーろがんつめたら
痛みが止んだというのは、この象牙質を作るという反応のために、起きる現象です。
(全部がそうだとは言いませんが、、、)
以上が歯の作られ方です。